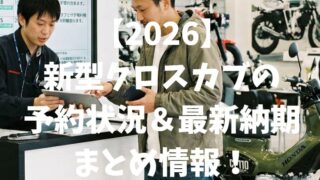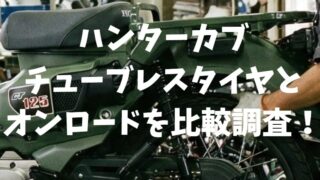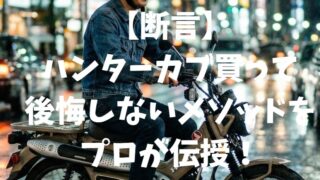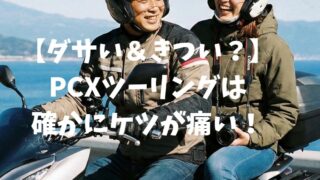ホンダ車
ホンダ車 【なぜない?】ハンターカブ/オイルフィルター交換&時期調査
ハンターカブのオーナーになったばかりのライダーが、初めてのオイル交換に挑戦しようとした際に必ずと言っていいほど直面する大きな混乱がある。。それは、オイルフィルターを取り付ける場所が、車体のどこを探しても見当たらないという事態です!なぜないのか?、と焦るハメになるオーナーも少なくない。。これは、ハンターカブのオイルフィルター交換をする以前の話になり、交換時期が近ずいて来れば、どうすればいいのかパニックになることも珍しくないはずだ。そこで、今回はハンターカブにおけるオイルフィルター設置場所のない謎を解き明かし、モデルごとの正しいフィルター交換方法と交換時期について徹底的に調査し解説していきます!