
「ホンダのCT125ハンターカブ、買おうか迷ってるんだけど、すぐに飽きちゃうって話も聞くんだよな・・」
あなたが今、そう感じているなら、それは決して珍しい悩みではないかも。CT125ハンターカブは、そのレトロで個性的なスタイルで人気を誇っています。
しかし、一方で「飽きる・・」「多すぎ・・」といった声を聞くことがあるのも事実です。せっかく手に入れたバイクが、あっという間にガレージの片隅で埃を被ることになるのは避けたい!
本当にハンターカブは飽きやすいバイクなのか? もしそうなら、その原因は何なのか?
この記事では、ハンターカブに「飽きる」と感じてしまう主な理由を徹底的に掘り下げ、長くハンターカブを楽しめるためのヒントを探っていきます。
人気ゆえの「飽和」問題や、購入後の「ワクワク感」の持続についてまで、ハンターカブオーナーのリアルな声やプロの視点も交えながら、多角的に検証していきます!
■この記事でわかること
- ハンターカブ/短期間で飽きる最大の原因8選
- 人気が故に多すぎて飽和?唯一無二の存在がゼロ?
- 2年も乗ればワクワク感が皆無になる?・・
- ハンターカブへの飽きを防ぐための具体策
- 最後に統括
ハンターカブ/短期間で飽きる最大の原因8選


CT125ハンターカブは、確かに魅力的なバイクですが、一部のオーナーが「短期間で飽きてしまった」と感じるのには、いくつかの明確な原因が存在します。
ここでは、その主な8つの理由を深掘りし、それぞれの背景にある心理を探っていきます。
想像以上の非力さに幻滅する
CT125ハンターカブは、排気量125ccの原付二種クラスであり、そのエンジンはスーパーカブC125をベースとした、あくまで実用域を重視した設計です。

街中でのストップ&ゴーや、ゆったりとしたツーリングには十分対応できますが、「速さ」や「加速感」を求めるライダーにとっては、想像以上に物足りなさを感じることがあります。
特に、普段から250cc以上のバイクに乗っている人や、スポーツ走行を好むライダーがハンターカブに乗り換えると、その非力さにがっかりすることがあります。
例えば、幹線道路での追い越し加速や、長い上り坂での登坂能力は、決して力強いとは言えません。
最高速度も、一般道法定速度を超える速度域では余裕がなく、巡航速度を維持するのも一苦労という場面も出てきます。
ハンターカブは、最高速度を競うバイクではありません。その魅力は、低速トルクと粘り強いエンジン特性、そしてどこへでも入っていける走破性にあります。
しかし、この点を理解せず、「どんな道でもスイスイ走れる万能バイク」という過度な期待を抱いてしまうと、実際の走行性能とのギャップに直面し、結果として「つまらない」「飽きた」と感じてしまうのです。
走行時の振動と疲労が蓄積する
CT125ハンターカブは、単気筒エンジン特有の鼓動感があり、これは魅力の一つでもあります。

しかし、長時間の走行や、特定の回転域での走行が続くと、シートやステップ、ハンドルから伝わる振動が予想以上に大きく、疲労感に繋がることがあります。
特に、長距離のツーリングでは、この振動が蓄積し、手や足の痺れ、腰への負担を感じることが少なくありません。
また、サスペンションも、悪路走破性を考慮して設計されていますが、舗装路での細かいギャップや段差では、突き上げ感が強く感じられることもあります。
これにより、乗り心地が期待ほど良くないと感じ、快適性の面で不満を抱く人もいるでしょう。
街乗り中心であれば大きな問題にはなりませんが、週末に数十キロ、あるいは百キロ以上のツーリングに出かけることが多い人にとっては、この振動や疲労がストレスとなり、次第にバイクに乗るのが億劫になり、「飽きる」原因となってしまうことがあります。
積載性の限界がキャンプやアウトドアの頻度を低下させる
CT125ハンターカブは、大型のリアキャリアを標準装備しており、キャンプやアウトドア用途に強いイメージがあります。
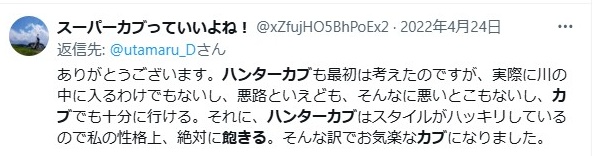
しかし、実際にキャンプ道具一式を積載しようとすると、意外と積載スペースが限られていることに気づくかもしれません。
大型のテントや寝袋、クーラーボックスなどを積むには、リアキャリアだけでは不足し、追加でサイドバッグやフロントキャリアが必要になることがあります。
また、そもそもキャンプやアウトドアに行く機会が、想像していたよりも少なかったというケースもあります。
購入当初は「キャンプに行くぞ!」と意気込んでいても、実際に準備や計画をするのが億劫になったり、仲間との都合が合わなかったりして、次第に頻度が低下していくことがあります。
そうすると、ハンターカブの持つ「アドベンチャー性」や「積載性」といった最大の魅力が活かされなくなり、単なる「ちょっとレトロな街乗りバイク」になってしまいます。
その結果、「このバイクでなくてもよかったのでは?」と感じるようになり、徐々に興味が薄れていってしまうのです。
カスタムの方向性を見失い深みにハマりすぎる
ハンターカブはカスタムパーツが豊富で、自分好みにカスタマイズする楽しみも大きな魅力の一つです。しかし、これが逆に「飽きる」原因となることもあります。
✅️一つは、カスタムの方向性を見失い、中途半端な仕上がりになってしまうケースです。
あれこれとパーツを付け足してみたものの、全体のバランスが悪くなったり、逆に使いにくくなってしまったりして、結局満足できないというパターンです。
理想のイメージが固まっていないまま手を出すと、パーツ代だけがかさんでしまい、達成感を得られずに飽きてしまうことがあります。
✅️もう一つは、カスタムの深みにハマりすぎてしまうケースです。
次から次へと新しいパーツを試したくなり、初期投資を大幅に上回る費用がかさんでしまいます。
最終的には、完成の目処が立たなくなり、カスタムそのものに疲れてしまったり、金銭的な負担から所有すること自体に嫌気がさしてしまったりする人もいます。
カスタムは楽しむものですが、沼にハマりすぎると本末転倒となり、それがハンターカブへの興味を失わせる原因となるのです。
日常使いでの不便さに直面する
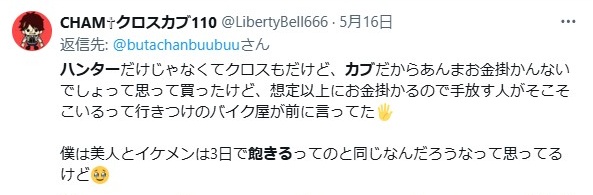
ハンターカブは、レジャー用途に特化したイメージがありますが、日常の足として購入する人も少なくありません。しかし、実際に日常使いを始めると、いくつかの不便さに直面することがあります。
例えば、多くのスクーターに標準装備されているフロントフックや、コンビニフックがないため、ちょっとした買い物袋を掛ける場所に困ることがあります。
また、シート下の収納スペースも、ジェットヘルメットがギリギリ入る程度で、フルフェイスヘルメットや多くの荷物を収納するのは困難です。
雨天時に走行すると、レッグシールドがないため、足元や車体が泥はねで汚れやすいというデメリットもあります。
これらの点は、事前に調べていれば分かることですが、実際に使ってみて初めて「こんなに不便だったのか・・」と感じ、日常のストレスとなってしまうことがあります。
その結果、次第に乗る機会が減り、他の利便性の高いバイクや公共交通機関に頼るようになり、「飽きた」というよりは「使いこなせない」という感情に陥ることがあります。
他のバイクへの興味が移る
バイク乗りの性(さが)とも言えますが、一台のバイクに乗り続けていると、他の魅力的なバイクに目移りしてしまうことはよくあることです。

特に、ハンターカブのような特定の用途に特化したバイクに乗っていると、「もっと速いバイクが欲しい・・」「もっと快適なバイクが欲しい・・」「もっと本格的なオフロードバイクが欲しい・・」など、異なるジャンルのバイクへの興味が湧いてくることがあります。
例えば、ハンターカブで林道走行の楽しさに目覚めた結果、より本格的なオフロードバイクにステップアップしたくなる。
あるいは、ツーリングの楽しさに気づき、長距離移動が快適なツアラーモデルに惹かれる、といったケースです。
これは、ハンターカブ自体に飽きたというよりも、ハンターカブでの経験を通して、自身のバイクライフにおける「次のステップ」が見つかった、と考えることもできます。
しかし、結果としてハンターカブに乗る頻度が減り、新たなバイクへの興味が加速することで、相対的にハンターカブへの熱が冷めてしまう、という現象は起こり得ます。
維持管理へのモチベーション低下
バイクは、車検の有無に関わらず、定期的なメンテナンスや清掃が必要です。
特に、ハンターカブはオフロード走行も想定されているため、泥汚れが付着しやすく、こまめな洗車やチェーンメンテナンスが必要になることがあります。
購入当初は、愛車のメンテナンスも楽しみの一つだったとしても、時間が経つにつれてその作業が面倒になったり、休日をバイクの整備に費やすのが億劫になったりすることがあります。
また、定期点検や消耗品の交換にかかる費用も、意外と積もれば大きな額になります。
こうした維持管理の手間やコストが、次第にライダーのモチベーションを低下させ、「乗るのが面倒・・」「維持するのが大変・・」と感じるようになり、結果的にハンターカブへの興味が薄れてしまう原因となることがあります。
特に、普段からあまりメンテナンスに時間をかけたくないタイプの人にとっては、この点が「飽きる」きっかけとなりやすいでしょう。
人気が故に多すぎて飽和?唯一無二の存在がゼロ?


CT125ハンターカブの人気は疑いようがありませんが、その人気の高さゆえに「飽和状態」となり、結果として「唯一無二の存在」という価値が失われたと感じる人もいます。
本当にそうなのでしょうか?
どこに行ってもハンターカブが多すぎる状況
CT125ハンターカブが発売されて以来、その売れ行きは非常に好調で、街中やツーリングスポット、キャンプ場など、どこに行ってもハンターカブを見かけるようになりました。
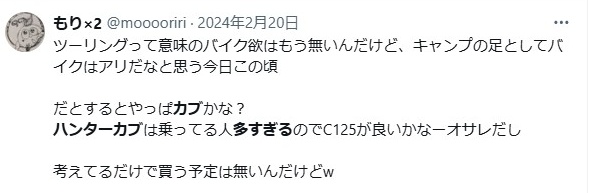
SNS上でも、多くのハンターカブオーナーが自身のカスタムやツーリングの様子を投稿しており、まさに**「ハンターカブだらけ」**と言える状況です。
かつては、ハンターカブのようなレトロオフロードスタイルのバイクは非常に少なく、所有しているだけで「個性的」「珍しい」と見られ、優越感を感じられる部分がありました。
しかし、あまりにも普及しすぎてしまった結果、その「珍しさ」や「特別感」が薄れてしまい、「他の人と同じ」という感覚に陥ってしまう人がいます。
これが、「飽和」という言葉で表現される状況であり、結果としてハンターカブへの興味が薄れてしまう原因の一つとなり得るのです。
特に、ファッションアイテムとしてバイクを捉えている人や、他人とは違う個性を強く求める人にとっては、この「かぶり」はモチベーション低下に直結する可能性があります。
個性が出しにくいと感じる
CT125ハンターカブは、豊富なカスタムパーツがあるため、本来は個性を出しやすいバイクであるはずです。
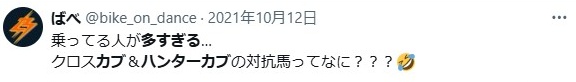
しかし、一部のオーナーが「個性を出しにくい・・」「唯一無二の存在じゃない・・」と感じてしまうのには、以下のような理由と錯覚が考えられます。
- カスタムが定番化
ハンターカブのカスタムには、人気のあるマフラーやキャリア、プロテクターなど、ある程度の「定番」とも言えるパーツが存在します。
多くの人が同じようなパーツを装着しているのを見ると、どんなにカスタムしても「結局はみんな同じような見た目になる」と感じてしまうことがあります。
- SNSでの情報過多
InstagramやX(旧Twitter)などで「#ハンターカブカスタム」といったハッシュタグを検索すると、驚くほど多くのカスタム事例が出てきます。
これらを見ることで、「もうやり尽くされている」「自分のアイデアでは、他の人と同じになってしまう」と感じ、独自性を出すことへのハードルが高く感じられることがあります。
- 理想の一台への過剰な追求
理想のカスタム像を高く設定しすぎると、どんなに手を加えても「もっと上のカスタムがある・・」「まだ足りない・・」と感じてしまい、いつまで経っても満足できないという状態に陥ることがあります。
しかし、プロの視点から言えば、これは錯覚に過ぎません。
ハンターカブのカスタムは、パーツの組み合わせだけでなく、カラーリング、ステッカーチューン、そして何より**「使い方」や「ライフスタイル」との融合**によって、無限の個性を生み出すことが可能です。
例えば、キャンプに特化した積載方法、釣り道具をスマートに搭載する工夫、あるいは特定のテーマ(ミリタリー、レトロ、ミニマリストなど)に沿った統一感のあるカスタムは、たとえ定番パーツを使っていても、乗り手の個性を十分に表現できます。
ハンターカブは、キャンバスのような存在です。そこにどんな絵を描くかは、乗り手自身のアイデアとセンスにかかっています。
「唯一無二の存在がゼロ」というのは、そのキャンバスの可能性を限定的に捉えているがゆえの誤解であり、少し視点を変えるだけで、自分だけの特別な一台を創造することは十分に可能です!
2年も乗ればワクワク感が皆無になる?・・


購入当初の「ワクワク感」は、どんなバイクでも時間の経過とともに薄れていくものです。
しかし、ハンターカブの場合、特に「2年も乗れば…」という声が聞かれるのはなぜでしょうか。
購入直後のハンターカブは、まさに**「新しいおもちゃ」**を手に入れたような感覚で、大きなワクワク感をもたらします。
- 新車特有の所有欲
ぴかぴかの新車を手に入れた喜び、独特の匂い、そして「自分のもの」になったという達成感。
- 未知の体験への期待
「これでどこに行こう?」「どんなカスタムをしよう?」といった、今後のバイクライフへの期待感。
- SNSでの情報収集と共有
他のオーナーの投稿を見て刺激を受けたり、自分のハンターカブの写真を撮って共有したりする楽しさ。
しかし、2年という期間は、バイクの運転に慣れ、基本的な走行性能や操作方法を体で覚えるには十分な時間です。購入当初の「真新しさ」は薄れ、良くも悪くも**「日常の一部」**となります。
どこへでも行けるという感覚も、実際に様々な場所へ行ったことで、新鮮味が薄れてしまうかもしれません。
この「慣れ」の段階で、新たな刺激や目標が見つからない場合に、「ワクワク感が皆無になる」と感じてしまうことがあります。
これは、ハンターカブに限らず、どんな趣味や所有物でも起こり得ることですが、ハンターカブの場合、そのシンプルな特性ゆえに、刺激を求める人にとっては慣れるのが早いと感じられるのかもしれません。
新たな所有価値の有無がカギ
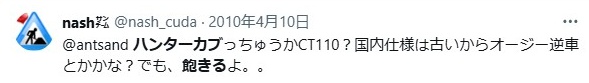
「2年も乗ればワクワク感が皆無になる」という状況を回避し、ハンターカブへの興味を持続させるためには、常に新たな所有価値を設定することが非常に重要です。例えば、
- カスタムのテーマを変える
これまで街乗り重視だったカスタムを、本格的なオフロード仕様に変えてみる。
- ツーリングのテーマを設定する
「日本百名林道制覇」「キャンプ場巡り」「ご当地グルメツーリング」など、具体的な目標を立てる。
- 仲間との交流を深める
ハンターカブオーナーズクラブに参加したり、イベントに参加したりして、共通の趣味を持つ仲間と情報交換をする。
このように、常に**「次は何をしよう?」という問いを自分に投げかけ、具体的な行動に移す**ことで、ハンターカブは常に新鮮な刺激を与え続けてくれる存在となります。
単に乗るだけでなく、「ハンターカブと共に何をするか」という視点を持つことが、ワクワク感を維持するカギとなるでしょう。
2年という期間は、そのバイクの特性を理解し、次のステップへ進むための準備期間だと捉えることができます。
ハンターカブへの飽きを防ぐための具体策


ここまで、ハンターカブに飽きてしまう主な原因を見てきましたが、ここからは、そうした「飽き」を防ぎ、長くハンターカブを楽しむための具体的な方法を提案します。
カスタムは「テーマ」を持って楽しむ
漠然とパーツを付け足すのではなく、明確なカスタムテーマを設定することで、一貫性のある、そして自分だけの唯一無二のハンターカブを創り上げることができます。例えば、
- 「ミリタリー」テイスト
カーキ色の外装に、無骨なツールボックスやジェリカン風のサイドバッグなどを装着。
- 「キャンプ特化」
大型リアキャリアにテントや寝袋を効率よく積載できるよう工夫し、使いやすさを追求。
- 「街乗りアーバン」
メッキパーツを多用し、おしゃれなシティコミューターとして仕上げる。
- 「アドベンチャー仕様」
アンダーガードやナックルガード、ブロックタイヤで悪路走破性を高める。
テーマを決めることで、どのパーツを選ぶべきか、どんな色合いにするべきかといった方向性が明確になり、カスタム沼に陥るリスクも減らせます。
また、完成した時の達成感もひとしおです。SNSなどで他の人のカスタムを参考にしつつも、最後は**「自分らしい」こだわり**をどこかに加えることで、愛着がさらに深まります。
用途を広げて「遊び」の幅を広げる

日常の移動手段としてだけでなく、ハンターカブの持つアドベンチャー性能を最大限に活かすことで、「飽き」を防ぐことができます。
- 林道ツーリングに挑戦
未舗装路や林道に入っていくことで、舗装路では味わえない景色やスリルを楽しむことができます。本格的なオフロードバイクでなくても、ハンターカブなら気軽に挑戦できるのが魅力です。
- キャンプツーリングを計画
ハンターカブに積める最小限のギアで、ソロキャンプや気の合う仲間とのキャンプを体験してみましょう。バイクと自然が一体となる体験は、日常では味わえない非日常感を提供してくれます。
- 釣りや写真など他の趣味と組み合わせる
ハンターカブは、釣り竿を積んで釣りに行ったり、カメラを持って景色の良い場所を探しに行ったりと、他の趣味との相性も抜群です。
バイクに乗ること自体が目的ではなく、その先の体験を目的とすることで、ハンターカブの活躍の場が広がり、飽きを感じにくくなります。
- 日帰り温泉巡りやご当地グルメ探訪
遠出しなくとも、ハンターカブで近隣の隠れた名所や美味しいお店を探しに行くなど、小さな冒険を日常に取り入れることで、新鮮な気持ちでバイクに乗ることができます。
他のハンターカブオーナーと交流する

同じハンターカブに乗っているオーナーと交流することは、「飽き」を防ぐ上で非常に効果的です。
- オーナーズクラブやSNSコミュニティへの参加
オンライン、オフライン問わず、ハンターカブのオーナーズクラブやSNSコミュニティに参加してみましょう。
共通の話題を持つ仲間との情報交換は、新たなカスタムのヒントになったり、ツーリングのお誘いに繋がったりと、刺激を与えてくれます。
- 合同ツーリングやミーティングへの参加
実際に他のオーナーと会って、カスタムを共有したり、一緒に走ったりする経験は、ハンターカブへの愛着を再確認させてくれます。
また、自分とは違う視点や使い方を知ることで、新たな発見があるかもしれません。
他者のハンターカブを見ることで、「自分もああしてみようかな」「こんな乗り方もあるんだ」といった、新たなモチベーションが生まれます。
また、一人でバイクに乗るだけでなく、仲間との共有体験が増えることで、バイクライフがより豊かになります。
定期的なメンテナンスと清掃で愛着を深める
バイクのメンテナンスや清掃は、単なる維持作業ではありません。愛車とのコミュニケーションの時間であり、定期的に行うことで愛着がさらに深まります。
泥や汚れを落とし、ピカピカに磨き上げることで、ハンターカブ本来の美しさを再認識できます。
チェーンメンテナンスで汚れを落とし、注油することで、エンジンのパワーがスムーズに伝わるようになり、走行性能も向上します。自分でメンテナンスすることで、バイクへの理解も深まります。
消耗品の点検や交換でタイヤの空気圧や溝、ブレーキパッドの減り具合など、日常的に点検することで、バイクのコンディションを把握し、安全に繋がります。
これらの作業を面倒だと感じるのではなく、「ハンターカブを大切にしている時間」と捉えることで、愛着がわき、長く乗り続けるモチベーションに繋がります。
最後に統括


「ハンターカブは飽きる」という声は、確かに存在します。
その主な原因としては、想像以上の非力さや振動による疲労、積載性の限界、カスタムの方向性を見失うこと、周囲との「かぶり」、日常使いでの不便さ、他のバイクへの興味、そして維持管理へのモチベーション低下が挙げられます。
特に、その人気ゆえに「どこに行っても同じハンターカブ」という状況が、「唯一無二の存在ではない」という感覚を生み出し、飽和感に繋がることもあります。
しかし、これらの「飽きる」原因は、ハンターカブそのものの本質的な問題ではなく、乗り手の期待値と、購入後のバイクとの向き合い方によって大きく左右されるものです。
ハンターカブは、決して「速さ」を追求するバイクではなく、その機能美と遊び心にこそ真の魅力があります。
購入当初の「ワクワク感」が薄れても、それはバイクに「慣れた」証拠であり、そこで終わりではありません。
むしろ、新たな目標を設定し、積極的に用途を広げ、カスタムを楽しみ、他のオーナーと交流することで、ハンターカブは常に新鮮な刺激を与え続けてくれる存在となります。
ハンターカブは、乗る人のライフスタイルを豊かにする無限の可能性を秘めたバイクです!
もしあなたが今、「飽きるかも」という不安を抱いているのなら、この記事で紹介した「飽き」の原因と対策を参考に、もう一度ハンターカブと真剣に向き合ってみてください。
そして、「好き」という気持ちを大切に、あなたの理想のハンターカブライフを思い描いてみましょう。
きっと、ハンターカブはあなたの期待を裏切らない最高の相棒となるはずです!
■ホンダ車の関連記事はこちら
- 【2026】ハンターカブ/現在の予約状況や納期が早まるのか?
- 【収納皆無】CB125R/リアキャリアの取り付けを解説!
- CB125R⇒「不人気」とネットで言われる本質をプロが解説!
- CB125Rをフルパワー化してパワー不足を改善する方法!
- リード125/適正なバッテリー交換方法を完全網羅で伝授!
- リード125の意外な欠点は足元が狭いってマジ?【プロ目線】
- なぜリード125に後悔の検索ワードがあるのか?【調査済み】
- CBR125RRとCBR125Rは全てが違う!マニア向け!
- CBX125カスタムの改造チョッパーがシブい!評価も上々
- CG125の耐久性やエンジン載せ替え時の注意点を解説!
- CBR125R/不人気の要因がヤバすぎ!なぜ売れなかった?
- CBR125R/パワーアップして最高速と馬力を上げる方法!
- CUV e:の充電方法や充電時間をくわしく徹底解説!
- 【どっちがいい?】リード125とPCX125の比較調査!
- リード125/風防対策で効果を検証!意外な結果が・・
- 【長距離NG?】リード125は山道走行で疲弊するのか?
- 【なぜダサい?】リード125がオッサンと言われる理由!
-
二級二輪整備士:大型二輪免許取得:愛車Lead125
125cc専門の情報発信者。各車種のスペックや走行性能、燃費比較からメンテナンスまで知識ゼロから詳しくなれるよう、すべてを“教科書レベル”で徹底解説しています!
- 2026年1月7日ホンダ車モンキー125にダサいおじさんが乗るのは正直イタい!?
- 2026年1月7日ホンダ車モンキー125に乗るかわいい女子ライダー5選!
- 2026年1月7日ホンダ車モンキー125は小さすぎるから危ない!?ガチな理由8選!
- 2026年1月7日ホンダ車モンキー125の飽きるしつまらないってぶっちゃけどうよ?

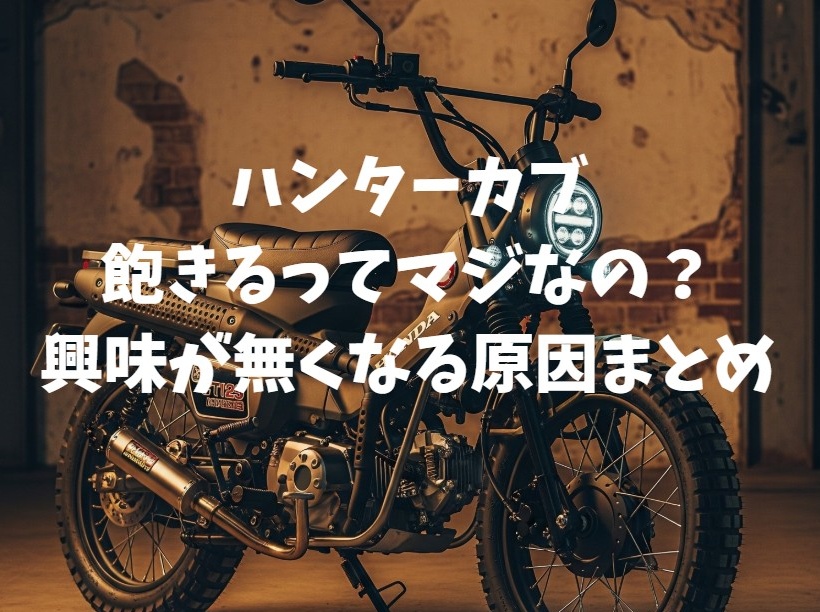
コメント