
バイクメーカーとして世界的な知名度を誇るカワサキ。しかし、一般的なイメージとして「KAWASAKIがスクーターを作っている・・」という印象は薄いのではないか?
街中で見かけるスクーターのほとんどは、ホンダ、ヤマハ、スズキといったブランドです。
なぜカワサキは、これほどまでにスクーター市場において存在感が薄いのか?
その裏には、単に「作らない・・」という単純な理由だけではない、カワサキという企業の哲学や戦略が深く関わっているのです。
ここでは、カワサキがスクーターを作らない背景や、市場に積極的に参入しない本当の理由を、多角的な視点から深掘りしていきます。
唯一のスクーターと言われる「J125」の不人気の背景や、海外市場での展開、そして今後の展望についても考察し、カワサキの「博学すぎる」戦略に迫ります!
■この記事でわかること
- カワサキがスクーターを作らない本当のワケが博学すぎた・・
- カワサキJ125が唯一のスクーター?しかも不人気・・
- Brusky125が販売されたが国内ではなくフィリピン・・
- 今後もスクーター部門は生産しないのか?
- 250cc以上のビッグスクーターは生産する噂も・・
- 最後に統括
カワサキがスクーターを作らない本当のワケが博学すぎた・・


カワサキがスクーター市場に本格的に参入しない理由は、一見すると不可解に思えますが、その背景にはカワサキならではの企業戦略やブランドイメージ、そして市場の現状に対する深い洞察があります。
ここでは、その「博学すぎる」ワケを5つ見ていきましょう。
カワサキブランドの確立と維持
カワサキは長年にわたり、「漢(おとこ)カワサキ」「乗り手を選ぶ」といった独自のブランドイメージを確立してきました。

これは、他社が万人受けを狙う一方で、カワサキは高性能でアグレッシブな、ある意味で「尖った」バイクを開発し、熱狂的なファンを獲得してきた歴史に裏打ちされています。
スクーターは、その性質上、幅広い層に「手軽な移動手段」として受け入れられることを目指した車両です。運転が容易で、積載性も高く、日常の足としての利便性が重視されます。
しかし、この「手軽さ」や「利便性」は、カワサキが培ってきた「操る喜び」「乗りこなす醍醐味」「圧倒的なパワー」といったブランドイメージとは、やや方向性が異なります。
スクーターを主力とすることで、これまでのブランドイメージが希薄になることを避けたい、という強い意志があると考えられます。
カワサキは、「誰でも乗れる」バイクではなく、「カワサキを選ぶ人だけが乗れる」バイクを提供することで、その独自のポジションを守ろうとしているのです。
リソースによる「選択と集中」戦略
バイクメーカーが新型車両を開発し、生産・販売するには、莫大な時間、資金、そして人材といったリソースが必要です。
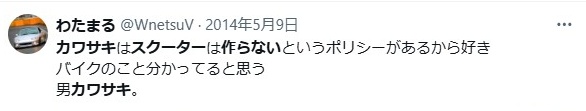
エンジン開発、車体設計、デザイン、生産ラインの構築、そして販売網の整備に至るまで、全てに高い専門性が求められます。
カワサキは、その限られたリソースを、自社の強みであるスポーツバイク、ネイキッド、オフロードといった分野に「選択と集中」する戦略を取っていると考えられます。
既に激戦区であるスクーター市場に後発で本格参入するには、莫大な投資が必要となり、他社との差別化も容易ではありません。
その投資を、得意分野の技術革新や新型モデル開発に充てることで、より効率的に競争力を高めようとしているのです。
スクーター市場でトップシェアを狙うのではなく、自社の得意分野で圧倒的な存在感を維持することに重点を置いていると言えるでしょう。
スクーター市場の飽和と収益性の課題
日本のスクーター市場は、既にホンダ、ヤマハ、スズキの三強が圧倒的なシェアを占め、市場が飽和状態にあります。

特に原付一種・二種クラスのスクーターは、価格競争が激しく、一台あたりの利益率が低い傾向にあります。
カワサキがこの市場に参入したとしても、先行する大手三社のような圧倒的な生産規模や販売網、ブランド力を確立するには相当な時間と費用がかかります。
また、技術面での大きな差別化も難しく、価格競争に巻き込まれる可能性が高いでしょう。
結果として、収益性が低く、投資に見合うリターンが得られないと判断している可能性が高いです。
収益性の低い市場に無理に参入するよりも、高付加価値の大型バイクや特定分野のバイクで安定した利益を確保する方が、企業戦略として合理的であると判断していると考えられます。
技術的蓄積と開発ノウハウの偏り
カワサキは、高性能エンジンや複雑なフレーム構造、そして先進的な電子制御技術など、スポーツ走行に特化した技術的蓄積と開発ノウハウを長年にわたり培ってきました。
例えば、スーパーチャージャー搭載エンジンや、トラクションコントロール、クイックシフターといった技術は、スクーターにはあまり必要とされないものです。
一方で、スクーターに求められる技術は、CVT(無段変速機)の開発、積載スペースの最適化、低速域での安定性、そして利便性を追求した装備など、スポーツバイクとは異なる分野のノウハウが必要です。
カワサキは、これらのスクーター特有の技術開発に、十分な経験やノウハウが蓄積されていない可能性があります。
ゼロからこれらの技術を開発するには、時間とコストがかかり、その分のリターンが見込めないため、あえて参入しないという判断を下していると考えられます。
ファン層へのコミット
カワサキには、「カワサキ乗り」と呼ばれる、非常に熱心で忠誠心の高いファン層が存在します。
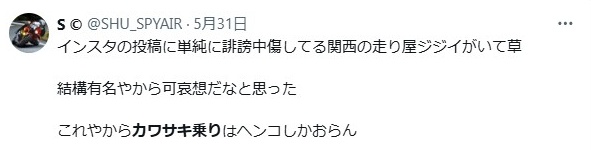
■カワサキ乗りとは?
カワサキのバイクに乗っている人のイメージとしては、全体的にいわゆる男っぽい雰囲気を持たれることが多いです。その一つの理由としては、昔からカワサキが好きだという中高年の男性が多いので、全般的に他のメーカーのファンよりも年齢層が上と感じることが多いからです。今までずっとカワサキ一本という方も多く、しかもカタナならカタナと、特定のシリーズにこだわっているものです。また、カワサキのバイクは重量感とパワーが強く、デザインもゴツイものが多いです。そのため、それに乗っているライダーも渋くてゴツイ雰囲気と見られる傾向があります。
彼らはカワサキのバイクに、単なる移動手段以上の「特別な何か?」を求めています。
それは、デザインであったり、エンジンフィールであったり、あるいはブランドが持つ哲学そのものであったりします。
カワサキは、これらのコアなファン層の期待に応えることを最優先していると考えられます。
彼らが求めるのは、やはり「走る楽しさ」「操る喜び」を追求したバイクであり、日常の足としてのスクーターは、彼らのニーズとは必ずしも合致しません。
カワサキがスクーターに注力することで、これまで培ってきたコアなファン層の期待を裏切ってしまうリスクを避けている、という側面もあるでしょう。
熱心なファンへのコミットメントが、スクーター市場への不参加という形に現れているとも言えます。
カワサキJ125が唯一のスクーター?しかも不人気・・


「カワサキはスクーターを作らない」というイメージが強い中で、唯一と言えるスクーターが、欧州市場向けに投入された「J125」です。
しかし、このJ125も、日本では正規販売されず、結果的に「不人気」という評価を受けることになりました!
Kymcoとの提携で誕生したJシリーズ
カワサキJ125は、純粋なカワサキ製スクーターではありません。

台湾の大手バイクメーカーであるKymco(キムコ)との提携によって誕生したモデルです。
Kymcoのスクーターをベースに、カワサキのデザインアイデンティティを取り入れたもので、フレームやエンジンなど、多くの基幹部品はKymco製が使用されています。
これは、カワサキが自社でゼロからスクーターを開発するのではなく、既にスクーター開発のノウハウを持つメーカーと提携することで、開発コストとリスクを抑えつつ、欧州市場のニーズに対応しようとした戦略の一環と言えます。
J125は、欧州で先行販売されていたJ300(こちらもKymco製)の弟分として登場しました。
日本市場での正規販売を見送った理由

J125は、欧州市場向けに開発・販売されましたが、日本では正規販売されませんでした。その理由としては、いくつかの要因が考えられます。
まず、前述したように、日本のスクーター市場が既に飽和しており、強力なライバルがひしめき合っている状況で、カワサキが後発で参入しても、大きなシェアを獲得することが難しいと判断した可能性が高いです。
Kymcoベースのスクーターにカワサキブランドを冠しても、日本のユーザーが求める品質や価格、そしてブランドイメージに合致しないと判断されたのかもしれません。
また、カワサキの日本国内における販売戦略が、やはり「スポーツバイク」「ネイキッド」といった既存の強みを生かすことに重点を置いていたため、あえてスクーター市場に投入する必要がないと判断したことも考えられます。
J125が投入されたとしても、カワサキのブランドイメージを損なうリスクや、既存の販売網での対応の難しさなども考慮されたでしょう。
「不人気」の背景にある要因
J125が欧州市場で「不人気」とされた背景にも、いくつかの要因があります。
まず、デザインの評価です。
カワサキの「Z」シリーズを意識したアグレッシブなデザインは、スポーツバイクとしては評価されても、スクーターとしては好みが分かれました。
スクーターに求めるのは、スタイリッシュさや日常的な使いやすさであり、J125の硬派なデザインが、幅広いスクーターユーザーに受け入れられなかった可能性があります。
次に、価格設定です。Kymcoベースでありながら、カワサキブランドを冠することで、同クラスのKymco製スクーターや、他社製品と比較して価格が高めに設定されていた可能性があります。
価格に見合うだけの「カワサキらしさ」が伝わりにくく、コストパフォーマンスの面で不利になったのかもしれません。
さらに、ブランドイメージとのミスマッチも影響したでしょう。
欧州でも、カワサキは高性能スポーツバイクのイメージが強く、スクーターにカワサキブランドを求める層が少なかったと考えられます。
スクーター市場で先行する他社ブランドに比べて、存在感が薄かったことも不人気に繋がったと言えるでしょう。
結果として、J125はカワサキのスクーター市場への挑戦としては限定的なものに終わり、その存在を知る人も少ない「不人気」モデルとなってしまったのです。。
Brusky125が販売されたが国内ではなくフィリピン・・


カワサキがスクーター市場に本格的に参入しないというイメージが強い中、2023年に突如として発表されたのが、新型スクーター「Brusky125(ブラスキー125)」です。
しかし、このモデルも日本国内での販売ではなく、フィリピン市場向けに投入されました。
新興国市場のニーズに合わせた戦略
Brusky125の投入は、カワサキが新興国市場のニーズに対応するための戦略の一環と見ることができます。

フィリピンをはじめとするASEAN諸国では、スクーターやアンダーボーン(カブのようなフレーム構造のバイク)が主要な移動手段であり、その需要は非常に大きいです。
日本や欧米のような趣味性の高いバイク市場とは異なり、生活の足としての実用性が重視されます。
カワサキは、これらの新興国市場において、これまで培ってきたスポーツバイクやネイキッドのブランドイメージだけでは、市場のシェアを拡大しにくいという課題認識があったと考えられます。
そこで、現地のニーズに合致したスクーターを投入することで、新たな顧客層を獲得し、市場での存在感を高めようとしているのです。
Brusky125は、カワサキが新興国市場に本腰を入れていることの証とも言えるでしょう。
現地生産と現地調達によるコスト削減
Brusky125は、フィリピンでの現地生産が主体となっています。

これは、部品の現地調達を進めることで、生産コストを抑え、現地の価格競争力に対応するための戦略です。
輸入に頼るよりも、現地で生産することで、関税や輸送コストを削減し、より手頃な価格で提供することが可能になります。
また、現地で生産することで、雇用を創出し、現地の経済に貢献する姿勢を示すこともできます。
これは、ブランドイメージの向上にも繋がり、長期的な市場戦略としては非常に有効な手段と言えます。
日本市場で正規販売されるJ125がKymcoベースだったのに対し、Brusky125は「カワサキの独自開発」とされている点が注目されます。
これは、カワサキが新興国市場向けに、スクーター開発のノウハウを蓄積しようとしている表れかもしれません。
日本国内での販売が見送られた背景
Brusky125がフィリピン市場向けに投入され、日本国内での販売が見送られた背景には、J125の時と同様の理由が考えられます。
まず、日本のスクーター市場の特殊性です。
日本では、原付一種・二種クラスのスクーターは、デザインや機能性、そしてブランドイメージにおいて、既に確立された強豪メーカーが存在します。
Brusky125がその市場で競争力を発揮できるか?、という判断があったでしょう。
また、Brusky125のターゲット層が、フィリピンなどの新興国市場における「実用性」を重視したものであり、日本のユーザーがスクーターに求める「スタイリッシュさ」や「先進性」とは異なる可能性があります。
日本市場に投入するには、さらに改良や仕様変更が必要となり、その投資に見合うリターンが見込めないと判断されたのかもしれません。
カワサキは、あくまで自社の強みであるスポーツバイクや大型バイクの販売に注力し、スクーターは特定の市場ニーズに合わせて柔軟に対応するという姿勢を示していると言えるでしょう。
Brusky125は、カワサキのグローバル戦略における「市場に合わせた柔軟な製品展開」の事例であり、日本国内でのスクーター事業展開には依然として慎重な姿勢を示していることを示唆しています。
今後もスクーター部門は生産しないのか?


これまで見てきたように、カワサキはスクーター市場において非常に限定的な参入姿勢を見せてきました。
では、今後もスクーター部門を本格的に生産することはないのでしょうか?
その可能性と、変化の兆しについて考察します。
作らない可能性が高い理由
現時点では、カワサキがスクーター部門を本格的に生産する可能性は低いと考えられます。その理由としては、以下の点が挙げられます。
✅️「選択と集中」戦略の継続
カワサキは引き続き、自社の得意分野であるスポーツバイク、ネイキッド、オフロードモデルに開発リソースを集中する可能性が高いです。
これらの分野で築き上げたブランドイメージと技術的優位性を維持することが、企業戦略の根幹にあるからです。
✅️市場の競争環境
日本を含め、主要なスクーター市場は依然として他社が圧倒的なシェアを占めており、激しい価格競争とブランド競争が繰り広げられています。
この市場に後発で本格参入するには、莫大な投資と時間が必要であり、採算性を確保するのが難しいと判断されるでしょう。
✅️ブランドイメージの維持
カワサキのコアなファン層が求める「操る喜び」や「走り」とは異なるスクーターを主力とすることで、これまでのブランドイメージが薄まることを避けたいという意向は強いと考えられます。
これらの理由から、少なくとも現在の主要市場(日本、北米、欧州)において、カワサキが大規模にスクーターを生産・販売することは考えにくいでしょう。
環境規制と電動化の波が影響
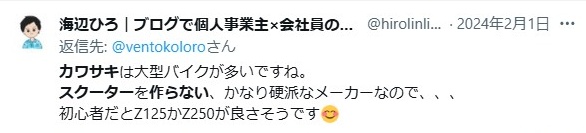
しかし、バイク業界全体に押し寄せている環境規制の強化と電動化の波は、カワサキの戦略に影響を与える可能性があります。
世界各国で、ガソリン車の販売規制や排ガス規制が強化されており、将来的には電動モビリティへの移行が避けられません。
電動スクーターは、都市部での移動手段として非常に有望な選択肢であり、静粛性や排出ガスゼロといったメリットがあります。
カワサキは、既に電動バイクの開発にも注力しており、一部の電動モデルを公開しています。
将来的には、これらの電動技術をスクーターに応用し、電動スクーターとして市場に投入する可能性はゼロではありません
。ガソリンスクーターでは競争が難しいとしても、電動スクーターであれば、新たな技術で差別化を図り、市場に参入できる余地が生まれるかもしれません。
ただし、これも「電動バイク」という枠組みの中での展開であり、「ガソリンスクーター」に特化した部門を立ち上げる可能性は低いでしょう。
特定の新興国市場での展開継続
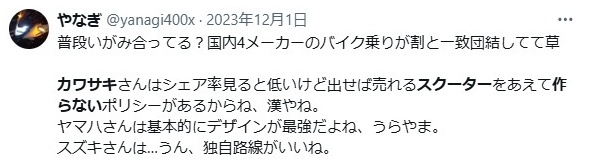
Brusky125の例が示すように、カワサキは今後も特定の新興国市場向けにスクーターを投入する可能性は十分にあります。
これらの市場では、スクーターが主要な移動手段であり、販売台数も非常に大きいため、ブランド全体の売上やシェア拡大に貢献できます。
新興国市場のニーズに合わせた低価格帯のスクーターや、現地の交通事情に合わせたモデルを開発し、現地生産・現地調達でコストを抑える戦略は、今後も継続されるでしょう。
これは、あくまでグローバル戦略の一環であり、主要市場でのスクーター部門の立ち上げとは別の動きと考えるべきです。
総じて、カワサキが今後も「スクーター部門」として大々的に事業を展開する可能性は低いですが、環境変化や市場ニーズの変化に合わせて、柔軟に製品を投入していく可能性は秘めていると言えるでしょう。
特に電動化の進展は、今後のカワサキのスクーター戦略に大きな影響を与えるかもしれません。
250cc以上のビッグスクーターは生産する噂も・・


これまでカワサキがスクーター市場に消極的である理由を解説してきましたが、一方で、「250cc以上のビッグスクーターを生産する」という噂も一部で囁かれています。
果たしてこの噂は本当なのでしょうか?
そして、その背景にはどのような可能性があるのでしょうか。
過去の提携モデル「J300」の存在
この噂の根拠の一つとなっているのが、J125の兄貴分である**「J300」の存在**です。

J300もJ125と同様にKymcoとの提携によって欧州市場向けに投入されたスクーターで、300ccクラスのビッグスクーターに分類されます。
J300は、J125よりも排気量が大きく、高速走行性能や積載性も向上しているため、欧州の都市間移動やツーリングにも対応できるモデルとして一定の評価を得ていました。
カワサキのデザインアイデンティティを前面に出し、スポーツスクーターとしての性格付けがされていました。
このJ300の存在から、「カワサキがビッグスクーターを開発する技術や意欲がないわけではない」という見方が生まれます。
しかし、これもKymcoベースのモデルであり、純粋なカワサキ製ではありません。
あくまで「提携」という形での市場参入であり、本格的な自社開発・生産とは異なります。
スポーツ性能と利便性の両立への挑戦?
もしカワサキが250cc以上のビッグスクーターを自社生産するとすれば、それは従来の「利便性重視」のスクーターとは一線を画し、「スポーツ性能」と「利便性」を高い次元で両立させたモデルとなる可能性が高いでしょう。

カワサキが持つ高性能エンジンの技術や、車体設計のノウハウをビッグスクーターに応用することで、これまでにない「走れるスクーター」を提案できるかもしれません。
例えば、ZシリーズやNinjaシリーズのようなアグレッシブなデザインを取り入れたり、高度な電子制御システムを搭載したりすることで、カワサキならではの「操る楽しさ」をスクーターで実現しようとする可能性も考えられます。
現在のビッグスクーター市場は、快適性や積載性だけでなく、走りにもこだわるユーザーが増えています。
そうしたニーズに応える形で、カワサキが独自の解釈でビッグスクーターを開発すれば、新たな市場を切り開くことができるかもしれません。
新規顧客層の開拓とブランドイメージ

ビッグスクーターの生産は、カワサキにとって新たな顧客層の開拓に繋がる可能性を秘めています。
例えば、大型バイクの免許は持っているが、スクーターの利便性も捨てがたい、あるいは、日常の足として使いつつ、週末にはツーリングも楽しみたいといった層です。
また、ビッグスクーターをラインナップに加えることで、カワサキのブランドイメージにも変化が生まれるかもしれません。
これまでの「硬派」「走りに特化」というイメージに加え、「幅広いニーズに応えるメーカー」という側面を打ち出すことができる可能性があります。
しかし、これは同時に、前述した「乗り手を選ぶ」というブランドイメージの希薄化にも繋がりかねず、カワサキが最も慎重になる点でもあります。
現状では、250cc以上のビッグスクーターをカワサキが本格的に自社生産するという具体的な計画は公表されていません。
噂の域を出ませんが、もし実現するとすれば、それはカワサキの企業戦略に大きな変化が訪れたことを意味するでしょう。
電動化の波や、多様化するユーザーニーズに対応するため、将来的にはあらゆる可能性を排除しないという姿勢の表れかもしれません。
最後に統括


カワサキがスクーター市場に積極的に参入しない背景には、「乗り手を選ぶ」という独自のブランドイメージの維持、自社の強みであるスポーツバイク分野への「選択と集中」戦略、飽和したスクーター市場の収益性の課題、そしてスクーター開発における技術的蓄積の偏りなど、多岐にわたる「博学的」な理由が存在します。
唯一のスクーターと言われる「J125」は、Kymcoとの提携によって欧州市場向けに投入されたモデルであり、日本での正規販売は見送られました。
その不人気の背景には、デザインの好みの偏りや価格設定、ブランドイメージとのミスマッチなどがありました。
近年発表された「Brusky125」も、日本国内ではなくフィリピン市場向けであり、新興国市場のニーズに合わせた戦略の一環と見ることができます。
現在のところ、カワサキが今後もスクーター部門を本格的に生産する可能性は低いと考えられます。
これは、引き続き「選択と集中」戦略を継続し、主要市場でのブランドイメージを維持しようとするためです。
しかし、電動化の波や、特定の新興国市場での需要拡大は、今後のカワサキのスクーター戦略に影響を与える可能性を秘めています。
一方で、「250cc以上のビッグスクーターを生産する」という噂は、過去の提携モデル「J300」の存在や、スポーツ性能と利便性の両立を求める市場ニーズを背景にしています。
もし実現すれば、それはカワサキの新たな挑戦となり、ブランドイメージにも変化をもたらすでしょう。
カワサキは、単に市場の流行に流されるのではなく、自社の哲学と戦略に基づいて、バイクのラインナップを構築していると言えます。
その結果が、「スクーターを作らない」という一見不可解な姿勢に繋がっているのです!
しかし、変化の激しい現代において、カワサキがどのような形でモビリティ市場と向き合っていくのか、今後の動向が注目されます!
■カワサキ車の関連記事はこちら
-
二級二輪整備士:大型二輪免許取得:愛車Lead125
125cc専門の情報発信者。各車種のスペックや走行性能、燃費比較からメンテナンスまで知識ゼロから詳しくなれるよう、すべてを“教科書レベル”で徹底解説しています!
- 2026年1月7日ホンダ車モンキー125にダサいおじさんが乗るのは正直イタい!?
- 2026年1月7日ホンダ車モンキー125に乗るかわいい女子ライダー5選!
- 2026年1月7日ホンダ車モンキー125は小さすぎるから危ない!?ガチな理由8選!
- 2026年1月7日ホンダ車モンキー125の飽きるしつまらないってぶっちゃけどうよ?


コメント